2.老犬でよく見られる病気

では、ここからは老犬で見られがちな病気について見ていきましょう。次に挙げたものは代表的な病気であって、他にもいろいろ注意を要する病気はあります。
1心臓疾患
【僧帽弁閉鎖不全症(僧房弁粘液腫様変性、僧房弁逆流)】
原因:
心臓から送り出される血液は、右心房→右心室→肺動脈→肺静脈→左心房→左心室→大動脈の経路を辿って全身に流れていきます。
このうち右心房と右心室の間には三尖弁と呼ばれる弁が、左心房と左心室の間には僧帽弁と呼ばれる弁があり、それぞれ血液の逆流を防ぐ働きをしています。
僧帽弁閉鎖不全症では僧帽弁に異常が生じることで血液の逆流が起こってしまいますが、その誘因としては加齢による僧帽弁の変性、弁を支える腱の緩みや断裂の他、心内膜炎のような他の心臓疾患からの併発などが挙げられます。
症状:
初期には症状らしいものは見られないことがあるものの、進行するにつれて咳、疲れやすい、活動性の低下、呼吸が速い、呼吸困難などの症状が見られるようになります。
末期になると肺水腫(肺に水が溜まった状態)を起こしたり、失神や昏睡に陥ったりすることがあり、最悪の場合は死に至ることもあります。
治療:
軽度では治療を必要としない場合もありますが、犬の状態によって強心剤や血管拡張剤、利尿剤などの内服薬を投与する他、外科手術が必要になる場合もあります。
予防:
残念ながらこれといった予防法はありません。しかし、肥満予防や塩分を摂り過ぎないように気をつける、負のストレスをかけ過ぎないよう配慮するなどは多少なりとも予防につながるでしょう。
2腫瘍・がん
【腫瘍・がん】
腫瘍・癌は脳、呼吸器、内臓、皮膚、骨、筋肉、血液、生殖器など体のいたるところに発生し、様々な種類があることから、ここでは「腫瘍・がん」として一括りにします。
そもそも腫瘍とがんとは何が違うのでしょうか? 結論を先に言えば、がんは腫瘍の一部です。腫瘍には「良性腫瘍」と「悪性腫瘍」があり、良性腫瘍は周囲組織との境がはっきりしており、比較的切除が容易で、多くの場合は再発せず、転移は見られません。
一方、悪性腫瘍は周囲組織に浸潤するように増殖するため、その境がわかりにくく、手術では周囲組織も含めて広めに切除する必要があります。加えて、腫瘍が大きくなるスピードが速く、血液やリンパの流れに乗って体の他の部位へ転移することがあるのも特徴的です。
そして、悪性腫瘍は「独立円形細胞腫瘍」と「固形がん」に大別できますが、前者は腫瘍細胞自体が独立して機能するタイプで、リンパ腫や肥満細胞腫、白血病、メラノーマ(悪性黒色腫)などが含まれます。
それに対し固形がんは体の組織や器官の特定部位に発生する塊状のものを指し、上皮細胞(皮膚や内臓、血管の表面を覆う組織)に発生したものを「~癌」と言って一般的には漢字で表記し、上皮細胞以外に発生したものは「肉腫」と呼んでいます。
ちなみに、良性腫瘍の場合は病名の最後が「脂肪腫」のように「腫」で終わることが多いようです。
以上のような分類はあるものの、一般的に「がん」と言った時には「悪性腫瘍」を意味すると捉えていいでしょう。
『良性腫瘍と悪性腫瘍の比較』
| |
良性腫瘍 |
悪性腫瘍 |
| 周囲組織との境 |
はっきりしている |
よくわからない |
| 増殖スピード |
遅い |
速い |
| 再発 |
少ない |
多い |
| 転移 |
しない |
する |
原因:
腫瘍・がんは一部の細胞の遺伝子が傷つき、異常な細胞が増殖していく病気ですが、特にがんの要因としては遺伝、ウイルス、炎症、薬物、食事、運動不足・肥満、汚染物質
(例:たばこ、殺虫剤)、ストレスなどいろいろ考えられています。
症状:
犬の腫瘍・がんには脳腫瘍から皮膚腫瘍、内臓の腫瘍、骨腫瘍、生殖系の腫瘍、リンパ腫など様々あり、腫瘍・がんの種類やできた部位などによって症状にも違いがありますが、一般的に以下のような様子が見られた時には何らかの腫瘍・がんの兆候である可能性が考えられます。
- しこりや隆起した部位がある
- 食欲不振、体重減少
- 元気消失
- 嘔吐、下痢
- リンパ節の腫れ
- 色濃い色素沈着
- 跛行
- 痛み
- 嗜眠
- 異臭
- 咳、呼吸困難
- 排泄がしづらい、出ない
- 発熱
- 貧血、出血 など
治療:
腫瘍・がんの治療では以下の3つが基本となりますが、
1.手術(腫瘍部分を切除)
2.化学療法(抗がん剤やその他治療薬を使用)
3.放射線療法(放射線の照射によってがん細胞の抑制や縮小を狙う療法)
この他に、
4.免疫療法(免疫細胞を活性化してがんの縮小を狙う副作用の少ない療法)(*1)
5.光線力学療法(光感受性物質を投与した後、レーザーをあてることでがん細胞の死滅を狙う体への負担が少ない療法)(*2)
などがあり、腫瘍・がんの種類や進行速度、ステージなどを考慮し、いくつかの治療法を組み合わせながら犬の状況や飼い主さんの希望に合わせた治療が行われます。
予防:
アメリカのVETERINARY CANCER SOCIETY(獣医がん学会)によると、犬の死因のトップは「がん」であり、4頭に1頭がいずれかの年代でがんを発症し、10歳以上の犬では約50%ががんになると推定されているそうです(*3)。
できれば予防したいものですが、バランスの良い健康的な食事を与え、適度な運動をして肥満を予防する、汚染物質を可能な限り避ける、負の強いストレスは与えないよう心がける、などは多少なりとも予防につながるでしょう。
3内分泌疾患
【甲状腺機能低下症】
原因:
甲状腺腫瘍や免疫系の異常などに起因し、甲状腺(喉の下部にある一対の腺組織)からのホルモン分泌が低下することで発症します。
症状:
痒みを伴わない左右対称性の脱毛、尻尾の脱毛(ラットテイル)、ふけ、皮膚の黒ずみや皺、皮膚トラブルを繰り返す、体重の増加、活動性の低下、震え、痙攣、斜頸、歩行障害などの症状が見られます。
犬では甲状腺機能低下症が多いのに対し、猫では甲状腺機能亢進症が多いとされますが、甲状腺ホルモンは新陳代謝に関わり、“元気”を左右することから、低下症の場合は活動性が低下し、亢進症では活動性が増すといった特徴があります。
治療:
甲状腺ホルモンの投与が主となりますが、甲状腺腫瘍が原因の場合は外科手術が必要になることがあります。
予防:
これと言った予防法はありませんが、早期発見のためには定期健康診断は有効となるでしょう。
【副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)】
原因:
下垂体や副腎の腫瘍、ステロイドの長期使用(医原性)などに起因し、副腎皮質(副腎の外側部分)から分泌されるコルチゾールと呼ばれるホルモンが過剰になってしまうことで発症します。
症状:
多飲多尿、食欲の増加、お腹が膨れる、筋肉の萎縮、左右対称性の脱毛、皮膚が薄くなる、皮膚の色素沈着などの症状が見られます。
糖尿病や膵炎などの合併症を起こすこともある他、原因が腫瘍であった場合、その場所や大きさによっては脳を圧迫し、認知症に似た症状が見られたり、状況によっては突然死に至ったりすることもあります。
治療:
治療は犬の状況により、内服薬の投与や手術、放射線治療、および医原性の場合は問題の薬の減薬などが行われます。
予防:
これと言った予防法はありません。ステロイド剤を使用する場合は、獣医師の指示を守って正しく使用する必要があります。
【糖尿病】
原因:
体の細胞にとって大切なエネルギー源となる血中の糖(ブドウ糖)は、本来、膵臓から分泌されるインスリンの働きによってコントロールされています。
ところが、インスリンがうまく働かなくなると糖を細胞内に取り込みにくくなり、その結果、高血糖の状態となって糖尿病を発症します。
糖尿病には2つの型があり、犬ではⅠ型が多いと言われますが、原因としては以下を挙げることができます。
①Ⅰ型:インスリン欠乏性
膵臓の機能低下によるインスリン量の不足
②Ⅱ型:インスリン抵抗性
膵臓やインスリンには問題がないものの、インスリンに対する体の反応が鈍い
糖尿病を起こす要因として、Ⅰ型の場合は遺伝や膵臓疾患、免疫異常などが考えられます。一方、Ⅱ型の場合はホルモン異常が関係しているため、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)のようなホルモン性の疾患、発情後、妊娠中、ステロイド剤やプロジェステロン剤の長期使用などが要因と考えられています。
症状:
初期には主に多飲多尿、食べるにもかかわらず体重が減少するといった症状が見られますが、進行して重度になると糖尿病性ケトアシドーシスと呼ばれる状態になり、嘔吐や下痢、食欲低下、元気消失、衰弱、脱水などの症状が見られるようになります。この状況は命にかかわるため、速やかな治療が必要です。
その他、糖尿病は進行すると白内障をはじめ、肝臓疾患や腎臓疾患など合併症を起こすこともあります。
治療:
インスリン製剤の注射、および食事療法が基本となり、定期的に血糖値を確認します。
基礎疾患がある場合は、その治療も同時に行います。
予防:
糖尿病を併発しやすい基礎疾患がある場合は、その治療を行うことが大事となります。また、運動不足や肥満、ストレスなどはリスクになるとも言われるので、適度な運動をし、ストレス回避を心がけることは予防につながるかもしれません。
4関節疾患
【変形性関節症】
原因:
変形性関節症とは、加齢や病気、遺伝的素因などによる関節軟骨の摩耗や関節への過度の負担、または関節自体の構造異常が原因となり、徐々に関節が変形してしまう病気です。
老犬に限らず、若い犬でも発症することがあります。
症状:
起き上がる時に動作がゆっくりで時間がかかる、段差や階段の上り下りを嫌がる、排泄の姿勢をとることが困難になる、動きたがらず寝ていることが多い、足先を引きずる、足を地面につけない、関節を舐めたりして気にしている、関節に熱や腫れがあるなどの様子が見られるようになります。
治療:
鎮痛剤や抗炎症剤などの投与と併せ、体重管理、関節を支える筋肉をつくるための適度な運動が大切となります。
その他、理学療法や湿布、鍼灸、マッサージなどを併用する場合もあります。
予防:
肥満や滑りやすい床は関節疾患にとってリスクとなるため、日頃より体重管理を行い、愛犬の行動範囲には滑り止めマットを敷くなど生活環境を整えることは予防につながります。
また、筋肉を維持するための適度な運動を心がけることも大事です。ただし、過度な運動は逆に関節を傷めてしまうことがあるのでご注意ください。
その他、シニア期になったならば、関節に良いとされるコンドロイチンやグルコサミン、コラーゲンなどのサプリメントを与えるのもいいでしょう。
5生殖器疾患
【子宮蓄膿症】
原因:
子宮蓄膿症は、子宮の中に細菌が入り込むことで子宮内に膿が溜まってしまうメス犬特有の病気です。
通常、健康であれば子宮に細菌が入り込んだとしても排除できるだけの力が備わっており、病気になることはありません。
しかし、発情中の排卵後には卵巣から黄体ホルモンが分泌され、その作用によって子宮頚管が閉じ、子宮内膜は受精卵が着床しやすいよう肥厚します。この状態になると子宮内部に入り込んだ細菌が子宮頚管から出て行きにくくなるのに加え、体の免疫力も弱まることから子宮内は細菌が繁殖しやすい状況となります。
黄体ホルモンの分泌は約2ヶ月続き、発情終了後3ヶ月くらいの間に発症が見られます。特に避妊手術を受けておらず、出産経験のない高齢のメス犬に多い傾向がありますが、若い犬でも発症することがあります。
症状:
初期には少し元気がない程度で目立った症状が見られないこともありますが、主に発熱、多飲多尿、陰部からの膿、陰部の腫れ、食欲の低下、元気消失、嘔吐、下痢、お腹の膨らみなどが見られます。
治療:
治療には子宮・卵巣を摘出する外科手術と、子宮収縮薬や抗生剤、点滴などを用いる内科的治療とがあります。
子宮蓄膿症は子宮に溜まった膿による子宮破裂や敗血症を起こす危険性があり、緊急手術となるケースは珍しくありません。
内科的治療は子宮から膿が出ている場合に有効であり、一旦治ったように見えても再発することがあります。
予防:
予防法があるとすれば、若いうちに避妊手術を受けさせることでしょう。
6神経疾患
【特発性前庭疾患】
原因:
前庭疾患とは、脳幹・小脳・内耳に障害が生じて平衡感覚を失ってしまう病気で、大きくは脳幹・小脳に障害が生じる「中枢性前庭疾患」と、内耳に障害が生じる「末梢性前庭疾患」に分けられます。
特発性前庭疾患は末梢性前庭疾患に含まれ、「特発性」とは原因が不明であることを意味します。
一つには、加齢にともなう代謝機能の低下によって前庭の内部を流れるリンパ液が滞るためではないかと考えられているようですが、詳しいことはわかっていません。
症状:
老犬に多く見られるこの特発性前庭疾患では、ある日突然または徐々に、眼振、斜頸、ふらつき、同じ方向にくるくる回る、起立困難などの症状が見られ、めまいを起こしたような状態になることから吐き気・嘔吐や食欲不振が見られることも珍しくありません。
治療:
犬の症状に合わせ、制吐剤やめまいを抑える薬、食欲がないケースでは水分やビタミン、ミネラルを含む点滴などを用いて対症療法が行われます。
斜頸がある場合は食事の補助、ふらつきや転倒がある場合にはケガをしないよう周囲を片付け、家具や柱には保護マットをあてがうなどの配慮が必要になります。
予防:
残念ながら、これといった予防法はありません。
7脳疾患
【認知症(認知機能不全症候群)】
原因:
認知症が起こる原因について、詳しくはまだわかっていませんが、犬の認知症は人間のアルツハイマー型認知症と似ており、脳細胞の酸素代謝の悪化や、アミロイドβと呼ばれる有害なタンパク質が神経細胞に蓄積すること、脳(前葉、側頭葉)の萎縮などが病因なのではないかと考えられています。
症状:
専門的には症状を次の6つに分けることができます。
| 1.見当識障害 |
- 狭い場所に入り込んで出られない(認知症ではなく、筋力の低下による場合もある)
- 左右どちら側にドアが開くかわからなくなる
- 徘徊する など
|
| 2.社会的交流の変化 |
- 名前を呼んでも反応しない
- 飼い主さんや同居ペットに対する興味が薄くなった
- 遊びに興味を示さない など
|
| 3.睡眠・覚醒サイクルの変化 |
- 夜間に度々起きる、なかなか寝ない
- 昼夜逆転
- 夜鳴き など
|
| 4.学習・記憶の変化 |
- トイレの粗相をするようになったなど、覚えていたしつけを忘れる
|
| 5.活動性の変化 |
- 無暗に吠え続ける
- 徘徊する
- 寝ているだけであまり動かない
- 食べることに興味がなくなる など
(活動性が増す場合と減る場合がある)
|
| 6.不安の増大 |
- 怖がりになった
- 飼い主さんの近くにいたがるようになった など
(これに関連して、怒りっぽくなったなど性格の変化が見られることもある)
|
ただし、老犬はストレスに弱く、不安になりがちであり、こうした様子が見られたからといって必ずしも認知症であるとは限りません。
治療:
犬の認知症は完治を望めるものではなく、いかに進行を遅らせ、少しでも改善をしつつつきあっていくかに重点が置かれます。
犬の状況によっては鎮静剤や抗不安薬、催眠効果のある薬、漢方薬、サプリメントなどが用いられる他、食事療法や心身に刺激を与えるアクティビティなどが取り入れられています。
予防:
以下のようなことは認知症の予防につながるでしょう。
①食事
認知症リスクを軽減させる効果が期待されているDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサぺンタエン酸) などのオメガ3脂肪酸を含む食事やサプリメントなどを与えるといいでしょう。
②運動
軽い運動は筋肉の維持やストレス発散などの他、心身に刺激を与えて脳の活性化が期待できます。散歩コースを時々変える、知育玩具を取り入れるなどもお勧めです。
③コミュニケーション
飼い主さんとのコミュニケーションは心身に刺激を与えます。その一つとして、お手入れのついでにマッサージを取り入れるのもいいでしょう。
④日光浴
特に朝の太陽を浴びることは体内時計をリセットし、睡眠の改善にも良いとされています。
8眼疾患
【白内障】
原因:
白内障は、眼の水晶体が白濁することで視力障害が起きる眼疾患です。
本来、眼の水晶体は透明なのですが、水晶体を構成するタンパク質に異常が生じて白濁が起こり、それに伴って網膜まで光が届きにくくなり、視力が低下します。
原因としては、
- 遺伝
- 加齢
- 外傷
- 糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)など代謝性疾患からの二次的発症
- 進行性網膜萎縮症やブドウ膜炎などの眼疾患からの二次的発症
- 中毒
- 薬物
などが考えられます。
症状:
白内障は状態によって4つのステージに分けられますが、初期には見えづらい程度なので飼い主さんでも気づきにくいかもしれません。
徐々に物や家具などにぶつかるなど視力の低下が見られ、重度になると痛みが見られたり、ブドウ膜炎や水晶体脱臼など他の眼疾患を併発したりすることも。放置すると最終的には失明に至ります。
治療:
軽度であれば進行を遅らせ、合併症を予防するための点眼薬や内服薬を用いた内科的治療が可能ですが、視力の回復が見込まれる場合には、白濁した水晶体を摘出して眼内レンズを挿入する外科的治療が選択肢となることもあります。
予防:
白内障の直接的な予防法はありませんが、抗酸化効果のある食品の摂取や強い紫外線を避ける、ケガ防止をこころがけるなどは予防につながると言われています。
すでに白内障を発症した初期段階の場合は、それ以上の進行を防止する目的の点眼薬が予防的に処方されることがあります。
また、白内障には先天性白内障と後天性白内障があり、前者では遺伝的素因が考えられているため、リスクがあるとされるアメリカン・コッカー・スパニエルやトイ・プードル、ジャック・ラッセル・テリア、柴犬、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルなどの犬種では、若いうちから眼の検査を受けるといいでしょう。
9口腔疾患
【歯周病】
原因:
歯周病は歯垢の中にいる細菌が歯周組織に入り込むことで発症します。
症状:
軽度では歯垢の付着や歯肉の赤みなどが見られますが、進行するにつれて歯石や口臭、歯周ポケットの形成、出血、痛み、歯のぬめり(細菌が作り上げるバイオフィルム)などが見られるようになります。
重度になると歯周ポケットから膿が漏れ出る歯槽膿漏の状態となり、さらに進行すると細菌が骨や皮膚まで溶かしてしまうことから外歯瘻(がいしろう:目の下や頬などの皮膚に穴が開いてしまった状態)、内歯瘻(ないしろう:口腔内に穴が開いてしまった状態)、口腔鼻腔瘻(こうくうびくうろう:口腔と鼻腔とを隔てる骨や組織に穴が開いて貫通してしまった状態)などにつながることがあります。
特に小型犬においては、歯の周囲の骨が細菌によって溶けて薄くなると少しの衝撃で顎を骨折する場合もあることには注意が必要です。
また、歯周病の細菌が血流に乗って全身に回ると心臓疾患や肝臓疾患、腎臓疾患などいろいろな病気に悪影響を与えてしまうことがあるため、特に持病を抱えることが多い老犬ではたかが歯の問題と軽く見過ごすことはできません。
治療:
歯周病の治療には歯垢・歯石の除去と、外科的治療(炎症によってダメージを受けた歯周組織を再生する歯周外科治療、および抜歯)があります。
重度の歯周病では無理に歯を残すよりも、犬のその後の生活を考えれば、歯周組織を少しでも良い状態で保つほうが良いと判断され、抜歯が行われることがあります。
予防:
歯周病では子犬の頃から歯のケアをすることが何よりの予防となるでしょう。
特に、老犬や小型犬、短頭種は歯周病のリスクが高いとされるので、日頃のお手入れの際には歯のチェックをすることをお勧めします。






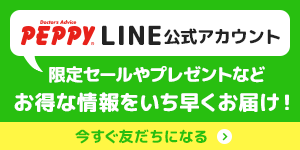



























監修いただいたのは…
2018年 日本獣医生命科学大学獣医学部卒業
成城こばやし動物病院 勤務医
獣医師 高柳 かれん先生
数年前の「ペットブーム」を経て、現在ペットはブームではなく「大切な家族」として私たちに安らぎを与える存在となっています。また新型コロナウィルスにより在宅する人が増えた今、新しくペットを迎え入れている家庭も多いように思います。
その一方で臨床の場に立っていると、ペットの扱い方や育て方、病気への知識不足が目立つように思います。言葉を話せないペットたちにとって1番近くにいる「家族の問診」はとても大切で、そこから病気を防ぐことや、早期発見できることも多くあるのです。
このような動物に関する基礎知識を、できるだけ多くの方にお届けするのが私の使命だと考え、様々な活動を通じてわかりやすく実践しやすい情報をお伝えしていけたらと思っています。