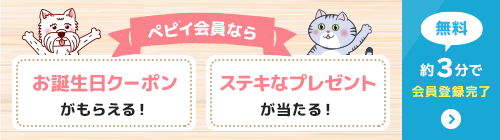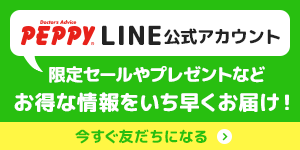VOL.22 熊本市動物愛護センター(ハロー・アニマルくまもと市)編
平成26年度に初めて犬の殺処分ゼロを達成!
動物たちへの思いを形に「即実行」で、動物愛護に取り組む施設
平成26年度に、犬の殺処分ゼロを達成した熊本市動物愛護センター。
そのニュースはたちまち日本中を駆け巡り、動物愛護関係者たちの注目の的となりました。原点は、職員さんたちの「どうすれば殺処分を減らすことができるのだろう」というごく純粋な動物たちへの思い。
その思いを現実へと導き、その後の熊本地震を乗り越えた、当センター職員さんたちの取り組みをご紹介します。
熊本市動物愛護センターのここがポイント
熊本空港から6キロほどの距離にある熊本市動物愛護センター。
東京ドーム4分の1個分の敷地からは、雄大な阿蘇山を望むことができます。
平成26年度、当センターが、犬の殺処分ゼロを達成したことは、大きなニュースとして発表され、動物愛護関係者たちの希望の扉を大きく拓きました。
きっかけは、職員さんたちの「どうすれば、殺処分を失くせるのか」という動物たちへの思い。その思いを現実にするため、関係者が話し合いの場を持つ動物愛護推進協議会が発足したのは平成14年のことです。

発足後は、飼い主への終生飼養について粘り強く説得をはじめ、迷い犬情報に写真を添えてホームページに掲載し、譲渡促進のために収容犬の個別管理・感染症対策・しつけ・トリミングを行い、動物愛護推進協議会と協働で動物愛護の普及啓発活動も行いました。
また、当センターに収容されるのは、迷子犬が多かったため、協議会で話し合った結果、迷子になる犬を徹底的に減らす取り組みを開始することに。平成21年には、当センターと動物愛護推進協議会が「迷子札をつけよう100%キャンペーン」を展開し、ケーブルテレビ(市民チャンネル)やその他のマスコミを駆使して「迷子犬情報の掲載」を行うなど、収容される犬の返還にも徹底的に力を注ぎました。
翌年の平成22年4月には、行政、地域住民が協働で行う殺処分ゼロへの取り組みが評価され、(公財)日本動物愛護協会主催の第2回「日本動物大賞グランプリ」を受賞。
これらの取り組みが功を奏し、平成23年度の犬の保護数は471頭(不要引き取りは含まない)で前年比を下回り、うち返還数が235頭と、半数が飼い主さんのもとへと帰ることができました。殺処分ゼロを達成できた平成26年度の返還数は保護頭数の実に6割にも上ります。その後も保護犬の返還数は増え、令和5年度は保護した犬の7割が返還されるまでに徹底され、飼い主さんへの啓発がいかに重要かを証明しました。

▲犬舎で保護されている犬たち

しかし、いいことばかりではありませんでした。
平成21年に動物愛護推進協議会が「殺処分ゼロを目指す」というスローガンを掲げ、そのニュースが報道された後から、収容される犬が増え、翌年には大幅に収容頭数が増加。「殺処分ゼロ」のニュースがきっかけで、動物愛護センターの敷地に犬が遺棄されることもあったのです。
それでも、根気よく啓発活動を続けた結果、センター内に犬を遺棄する人もいなくなり、収容頭数もどんどん減って、この10年で4分の1にまで減少しました。
「飼い主さんへの啓発がいかに大切か、迷子札キャンペーンの徹底でよくわかりました。また、当センターは平成26年度、初めて犬の殺処分ゼロを達成しましたが、これはあくまで結果であって、殺処分ゼロは厳守すべきものとは考えていません」
そう語ってくれたのは、当センター所長で獣医師の瀧本勉さん。
瀧本さんが指摘するように、平成26年度以降も犬の殺処分があった年はいくつかあります。
「殺処分ゼロ厳守で業務を行うと、そこに必ずひずみが出てきます。攻撃性が強いなど、市民の方に譲渡できない犬は、やはり殺処分するしか他はありません。人が飼えないような犬を “はい、どうぞ”と容易に渡すことは、我々はできないわけです。殺処分ゼロはあくまでも、終生飼育や迷子対策などの啓発の成果、収容頭数の減少、譲渡推進の結果であるべきです」

結果としての「殺処分ゼロ」とは「殺処分する必要がない状況」に至ることです。
ベストなのは、動物愛護センターに収容される命がゼロになることでしょう。またゼロにならなくても、その数が著しく減少すれば、馴化トレーニングなども丁寧に行うことができ、すべての犬猫に新しい飼い主さんを見つけるチャンスが広がります。結果、殺処分など必要なくなるのです。
そのためには、迷子札に続き、飼い主からの安易な引き取りを減らすための、終生飼育等の啓発が最重要ポイントとなるのです。
現在では、センター職員さんや、動物愛護推進協議会、多くのボランティアさんの熱心な取り組みが功を奏し、令和元年から、犬の殺処分ゼロを継続しています。
また、譲渡対象であったにも関わらず、縁に恵まれなかった犬たちは、長期収容でも必ずしも殺処分対象になるとは限りません。多頭飼育崩壊現場から生後4,5か月でやってきたブリちゃんは、人とのふれあいが大の苦手でこれまで飼い主さんとの縁が結びつかなかった犬。その後、14年間、ずっとセンターの中で暮らしています。
殺処分決定となる犬は、あくまでも、攻撃性が強い犬など、人間と暮らしていくのが困難な犬に限っていることも当センターの特徴です。

▲犬舎内のブリちゃん
「うちのセンターにいる犬は、中型以上の雑種が多いので飼い主さんが見つかりづらい。またもし、飼い主希望者さんが現れても、譲渡には約束事が多いので、希望者さんにウンザリされてしまうこともあります。確かに譲渡条件は多々ありますが、ここにいる子たちには二度と辛い思いをしてほしくない。確実に幸せにしてくれる飼い主さんのもとへいって、今度こそは絶対に幸せになってほしい・・・それが、私達職員の願いなんです」
飼い主さんたちの要望や、満足だけではなく「動物たちの幸せがその家にあるか」を、常に考えながら、職員さんたちは日々の譲渡活動にも力を入れています。
近隣自治体、市民とのスムーズな連携で、熊本地震を乗り越える!
平成28年4月16日-。規模マグニチュード7.3の大地震が熊本市を襲いました。
家屋の被害状況は136,695件に上り、震源地の益城町から数キロしか離れていない当センターでもよう壁が崩れ、敷地内に地割れが起こり、ライフラインはすべて断絶しました。
幸い、職員さん、収容犬猫は無事でしたが事務所内の壁には亀裂が入り、書棚やパソコン、机などはすべて転倒し、通常通りの業務ができない状態で、動物収容室の清掃も、職員が水を汲みに行ったり、給水車に頼って行うしかありませんでした。
そんな状態の中で、今後増えると思われる被災犬猫の保護をどうするかが目の前の課題でしたが、市内の動物病院も多くが被災していて、被災動物を預かれる状況ではありません。
被災した犬猫の受け入れのためには、当センターで収容中の犬猫を減らす必要があります。そんな中、当センターの犬猫の受け入れに、真っ先に救いの手を差し伸べてくれたのは、北九州市動物愛護センターで、発災わずか4日後の4月20日には、26頭の犬猫が北九州市動物愛護センターに移送。次いで、4月27日、28日には環境省の仲介で他の26府県市の自治体に29頭の犬猫が無事、移送されました。

▲同センター内にある慰霊碑
一方、当センターでは、ペットとともに被災した市民の現状を把握し、少しでもサポートしていく必要がありました。
「市民の方々の中には、地震で逸走した迷子犬・猫を保護し、そのまま自宅で預かってくれたり、協力を申し出てくれたりする人が多く、本当に救われました。結果、センターに収容される動物もそれほど多くならずに済んだのです。また、環境省の仲介で、具合が悪くなって緊急入院した飼い主さんなどの犬猫の一時預かり体制を作ることができました。特に被災された飼い主さんのサポートについては、被災者に寄り添う動物愛護推進員さんの協力が大きかったですね」
市民一人ひとりが、それぞれの判断に応じ、できることを担うことで、臨機応変に被災動物や飼い主さんたちをサポートすることができたと瀧本さんは言います。
また、大災害の渦中においても「殺処分ゼロ」を目指すために、動物愛護推進協議会と展開していた迷子札キャンペーンが大きく功を奏し、地震の衝撃で逸走した犬猫たちの多くが、保護後に飼い主さんのもとへ早々に帰ることができたのです。
その後、他の自治体に移送された犬猫たちも、移送先で譲渡が決定。
「移送先の動物愛護センターで、譲渡先が見つからなければ、復旧後にこちらに返してもらう予定でしたが、移送先で、新しい飼い主さんを見つけてもらうことができました」
このように市民や他の自治体とのスムーズな連携あってこそ、あの大災害を動物たちと共に乗り越えることができたのです。
熊本市動物愛護センターの課題は猫
他の自治体と同じく、当センターの課題は幼齢猫の収容と地域猫活動の推進です。
ここ数年の幼齢猫の収容割合は全体の5割。6割を超える年度もあります。そこで当センターでは平成27年度から「ミルクボランティア制度」を導入。現在では30名ほどの登録ミルクボランティアさん(常時稼働は10名ほど)に幼齢猫の世話をしてもらい、離乳期が終わった時点でセンターに戻してもらってから、飼い主さんを募集します。
特に注意が必要な子犬・子猫などは、当センターの職員さんも手分けして、自宅に連れて帰り世話を担うことも少なくありません。

▲猫舎で保護されている猫たち
技術主幹の後藤隆一郎さんもその中のひとり。
収容された子犬と子猫を自宅に連れて帰って世話を始めたところ、日に日に愛情が沸き、子どもたちに「返さないで!」とおねだりされたことから、そのまま後藤家の家族に。
その時に子犬だったミックス犬のアンちゃんは現在11歳。子猫だった、ブブたんは15歳となり、後藤さんの子どもたちも立派に成長しました。このように、後藤さんの家族となったアンちゃんやブブたんは、非常にラッキーですが、職員さん自身が面倒を見ることができる犬猫は氷山の一角。毎年春から秋にかけて、どんどん収容される幼齢猫の世話は、ミルクボランティアさんの手を借りなくてはできないのが現実なのです。
また、こういった子猫を次から次へと産んでいるのが野良猫で、これら飼い主のいない猫への対策も待ったなしです。
そこで熊本市は令和3年、地域猫適正管理推進事業を2か年のモデル事業として開始。翌4年には(公財)どうぶつ基金と協働で、TNR地域集中プロジェクトを実施しました。
その後は、TNRに対する市民のニーズが強まり、地域猫活動に取り組み地域も増加したことから、令和5年より市民が捕獲した飼い主のいない猫の不妊去勢手術を、当センターで独自で実施する取り組みを開始。繁殖による増加を抑制するとともに、地域猫活動推進にも積極的に取り組んでいます。

また最も大切なのは、野良猫に餌を与えるならば、周囲に迷惑がかからないようにし、猫で迷惑している人がいれば丁寧に説明をして理解を求めていく体制です。
「TNRをすることにより、あれ、猫が減っている、猫がこれ以上増えないんだね!という声も、猫で困っていた方から届くようになり、理解いただけるようになりました。地域猫活動は、猫が好きな方にとっても、猫で困られている方にとっても、両者のためになることを丁寧に伝えていくことが成功のカギだと思います」と、瀧本さん。
そもそも野良猫は、飼い猫が捨てられたり、不妊去勢していない飼い猫が家と外を自由に出歩いたりして繁殖した結果なのです。その原因は、私達人間社会にあります。だからこそ特定の誰かに責任を押し付けるのではなく、地域全体で地域猫活動を推進し、一代限りの命を大切に見守ることが、原因を作った私たちの責任でもあるのです。
熊本市動物愛護センター 所長の瀧本勉さんに聞きました!
取材に応じてくださった技術主幹の後藤さん同様、所長の瀧本勉さんも保護犬を家族として飼い、その一生を見届けたひとりです。
現在では、馴化が難しいセンターの猫、推定8歳のミルリールちゃんを自宅に連れて帰り、日々人馴れするためにトレーニングに励んでいます。

▲技術主幹の後藤隆一郎さん(左)と所長の瀧本勉さん
ミルリールちゃんは人を噛む癖があり、瀧本さんも何度か噛まれたことがあると言います。
「まずは、少しでも噛み癖を改善して、いい飼い主さんを見つけることが目標です。当センターのスタッフはみんな動物が大好き!ミルリールは成猫ですが、幼齢猫が入る時期にはミルクボランティアさんに頼るだけではなく、職員たちも自宅に子猫を連れて帰って世話をしていますよ。日々動物たちと接しながら、その命と向き合っている私達職員が願っていることはひとつ。それは、人と動物が共生できる、安全で安心な、住みよいまちづくり―。
ところが動物を介して人と人がトラブルになることがまだまだ絶えません。課題となっている地域猫活動でもそうですが、猫に餌を与える方VS猫で迷惑されている方、という形で対峙が始まり、やがてトラブルに発展してしまう。
動物のためにも、人間同士がいがみ合うことだけは本当にやめて欲しい・・・。それが私の切なる願いです。
また現在、大きな課題となっているのが、高齢者が飼育している犬猫の問題です。
当センターでは昨今、飼い主から引き取るケースとして高齢飼い主の長期入院や施設入所、死亡を理由とする件数が増加傾向にあります。離れて暮らす親族から、犬猫の飼育を継続できないが、どうすればよいかと相談を受けることもありますが、今後、こういった問題をどう解決に導いていくのかも、考えて行かなくてはなりません」

▲瀧本さんが自宅でトレーニングしているミルリールちゃん
滝本さんは何度も強調して言います。
人と動物が幸せに共生できる社会こそが、目指すべき社会であると―。
社会的弱者と言われる子ども、老人、そして、犬猫たちが幸せな社会は、本当に誰にとっても幸せな社会に繋がるのではないでしょうか―?
あの熊本地震をも乗り越えた、熊本市動物愛護センター。
これまでのように、動物たちへの思いを、即実行すれば、その願いはいつか、必ず実現するはずです
(取材:2024年12月)
熊本市動物愛護センター
ハロー・アニマルくまもと市
住所:〒861-8045 熊本県熊本市東区小山2丁目11-1
電話:096-380-2153

取材・記事:今西 乃子(いまにし のりこ)
児童文学作家/特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会理事/公益財団法人 日本動物愛護協会常任理事
主に児童書のノンフィクションを手掛ける傍ら、小・中学校で保護犬を題材とした「命の授業」を展開。
その数230カ所を超える。
主な著書に子どもたちに人気の「捨て犬・未来シリーズ」(岩崎書店)
「犬たちをおくる日」(金の星社)など他多数。