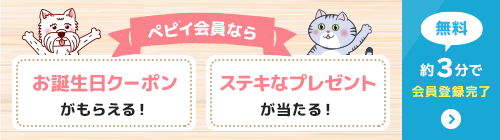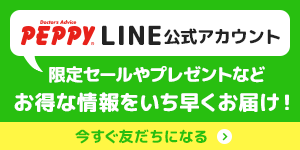VOL.7 神奈川県動物愛護センター 編
キーワードは、収容された犬猫たちの「心を磨き、体を磨く」。
「動物を処分するための施設」からセカンドチャンスの可能性を広げる「生かすための施設」へ―。
神奈川県平塚市の自然豊かな緑の中に位置する神奈川県動物愛護センター。
この施設は令和元年6月に「動物を処分するための施設」から「生かすための施設」へとリニューアルオープンしました。
そのスローガン通り、当施設は平成26年度(犬は平成25年度)から「殺処分ゼロ」を継続。新しい施設には、殺処分機はありません。
その「殺処分ゼロ継続」を支える柱のひとつが、「かながわペットのいのち基金」。

▲ かながわペットのいのち基金 ※クリックで画像を拡大
これは、行き場のない犬猫たちの命を救いたいと願う、多くの人たちからの願い(寄附金)を受け、当センターで保護されている犬や猫たちの新たな飼い主探しのために役立てられます。
そして、もうひとつは施設職員さんと、ボランティアさんとの見事な協力体制です。
「できる人」が「できること」を―。
多くの人の「できること」が紡いだ「殺処分ゼロ」の舞台裏をご紹介します。

▲ 犬や猫だけでなくいろんな動物達が保護されている
「神奈川県動物愛護センター」のここがポイント
保護された犬・猫の明日を繋ぐ「心と体をピカピカにするプロジェクト」!
昭和47年に「神奈川県犬管理センター」として開設された、現在の神奈川県動物愛護センター。当時は年間20,000頭の犬を収容し、ほとんどを殺処分していたと言います。
「この地域の人たちは当初から野犬に対する危機感が強く、駆除願いの通報も多くて、捕獲が徹底して行われていました」と、当センター課長の上條光喜さん。
現在では収容される犬の数は年間319頭(令和元年度)で、そのうち野犬とみられる犬はゼロ。そして昭和55年度から収容し始めた猫も、年間最大13,000頭以上におよび、そのほとんどを殺処分していましたが、現在は443頭(令和元年度)の収容となっています。犬では半数近くが迷子犬で飼い主に返還されるため、残るのは600頭ほど。
当センターでは、登録ボランティアさんが積極的に保護された犬や猫を引き出して、新しい飼い主さんを探しており、センターで飼い主探しや譲渡まで世話をするのは、一年間で230頭ほどです。この数だけ見てみると「殺処分ゼロ」は難しくないと思うかもしれませんが、譲渡達成の問題点は、数だけではありません。
手入れが行き届き、冷暖房完備の施設内に並ぶ犬舎では「咬む!」と書かれた犬舎が少なからず見られます。中には皮膚病や病気の犬の姿も―。
こういった犬たちは「譲渡」することが難しく、動物愛護センターによっては殺処分対象となります。人間に馴れず、危害を与えるとわかっている犬をセンターの職員さんが「はい!どうぞ!」と渡すことなど絶対にできません。また病気でこの先、治療費がどれだけかかるのか、どれほど世話がかかるのかわからない犬を「喜んで!家族にします」という人もめったにいないでしょう。


では、当センターではどのような方法を経て「殺処分ゼロ」を継続しているのでしょうか―。「生かすための施設」とスローガンをあげているのだから、センターでこの先ずっと面倒を見るのでしょうか?それは大きな間違いです。
「生かすための施設」の本当の意味は「譲渡できない犬猫をここで一生面倒見る」という意味では決してありません。犬や猫の本当の幸せとは「家族として、飼い主さんに愛され、死ぬまで一緒に暮らすこと」。
当センターでは、すべての犬猫の「心と体」を良い状態に整え、良い飼い主さんを見つけて「譲り渡す」ことを最終目的にしています。
ここで大きな役割を担ってくれるのが、柱のひとつとなる「かながわペットのいのち基金」。
先にあげた問題行動や病気の治療が必要な犬や猫の「心をピカピカにして、体をピカピカにする」に使われる寄附金です。
「人間が信頼できず咬む」「唸る」「しつけが全くできていない」など、様々な問題行動を起こす犬にはプロのトレーナーさんが定期的に訪れ、人馴れや人と暮らすためのしつけを行います。
その時に、センター職員さんも一緒にトレーニングに参加。プロのトレーニングを日常に引き継ぎ、そのトレーニングに努めます。
こうして犬が徐々に人間を信頼しはじめ、咬む、怯えるなどの問題行動が改善されれば、飼い主さんの募集を開始します。
それでも問題行動が取り除けない犬に対しては、その原因をきっちりと把握し、新しい飼い主さんに丁寧に説明し、了解を得たうえで譲渡をします。
また、病気やアレルギーの犬猫たちには、(公社)神奈川県獣医師会の獣医師の協力も得て、治療を行います。この場合もセンター職員の獣医師さんは、治療技術を臨床専門の獣医師たちから学ぶことを怠りません。自分たちもできる限り治療技術を身に着け、ここにやってくる犬猫の治療に全力で当たりたいと考えたからでした。
これらの犬・猫も怪我や病気が治れば、飼い主さんの募集を開始し、完治が難しい犬・猫に対しては、新しい飼い主さんにその病気とうまく付き合っていくための情報や助言をして譲渡に結びつけます。

▲ 保護された犬・猫

「病気の子たちの中には、継続して治療が必要な子や、片目がない子などもいますが、今後どれくらいの治療が必要で、どれくらいの世話が必要なのかをきちんとお伝えすれば、時間がかかっても、家族に迎えてくださる方は必ずいるんです。そして、そういった子ほど、大切にされ、幸せになっています」
課長の上條さんは、さらに続けます。
「大切なのは、犬猫を受け入れるための判断基準、つまり、細かい情報を飼い主希望者さんにきちんとお伝えすることです。それと、忘れてはならないのが、ボランティアさんの存在です。ここに来た犬たちを自宅等で保護して新しい飼い主さんを見つけてくださる預かりボランティアさんはもちろん大きな助けですが、中には先が短いことをわかっていて引き取ってくださるボランティアさんもいらっしゃいます」

昨今では老犬や病などで先がない犬猫をセンターから引き取る「ボランティア」もいると言います。
一見、辛い務めに思えますが、自分自身が高齢で、新しい犬・猫を飼うことができない、何らかの事情で長期飼育ができない人が「今まで自分に幸せをくれた犬猫への恩返し」として、そのようなボランティアを始めることもあるのです。
どのボランティアも楽なことではありませんが「人間にたくさんの幸せをくれた犬猫のために何かしたい」と考える人たちの優しさや思いがぎゅっと込められています。
「殺処分ゼロが継続できるのは、募金をしてくださる方や、ボランティアさんたちが頑張ってくださるからです。しかし、ここに入ってくる犬猫の数が増えればそれも難しくなる。救いの受け皿を広げるのは限界があります」
センター開設当時の野犬駆除や20,000頭の殺処分をどう考えるかは人それぞれです。
しかし、当時の徹底した野犬捕獲があったからこそ、それ以降、不幸な命が作り出されることもなく、センターに収容される犬猫の数も激減したのです。その結果が40年近く経って、ようやく功を奏し、犬猫の命を絶つことなく、命のバトンを繋げるまでになったのでしょう。一時の「かわいそう」はもっとたくさんの「かわいそう」を作ってしまいます。「かわいそう」を最小限にとどめる勇気が時には必要です。そして、二度と「かわいそう」な出来事を作らないことです。

▲ 同センター内の動物慰霊碑
命を絶つことに達成感を感じる人はいません。
人であれば誰しも、命を救い、守ることに喜びを感じるはずです。
その喜びのために、職員さんも、ボランティアさんも日々、走り、奮闘しています。
課長の上條さんは、センターの敷地内にある動物慰霊碑の前で、手を合わせ、こう言いました。
「定期的にここに来て、しっかりと手を合わせて拝んであげないとね・・・。がんばって命のバトンを繋ぐからと、天国へ行った犬猫たちに報告するんです」
動物慰霊碑の周囲は、職員さんによって花が植えられいつもきれいにされています。
「ぼくら職員だけじゃないですよ。たくさんの方々がここに足を運んで、フードや花やお菓子などを添えてくださる。みな同じ気持ちです」
命を繋ぐ、「神奈川県動物愛護センター」のボランティアさん
平成26年度からの「殺処分ゼロ達成」を継続するため、大きな役割を担っているのが当センターに登録しているボランティアさんです。
犬猫を引き出し、自宅等で預かってその後新しい飼い主さんを見つける「譲渡ボランティア」他、シャンプーやトリミングなどを行う「グルーミングボランティア」、啓発をする「動物愛護普及啓発ボランティア」など、その数は団体、個人含めると61ボランティアでセンターと密に連絡を取り、フル稼働で協力しています。
特に大変なのが、春から秋。猫の出産シーズンのため、毎年多くの幼猫が収容されます。当センターで収容される猫の数は年間443頭(令和元年度)で約半数以上が幼猫。
3月末頃から11月頃まで、季節変動はありますが、毎月約30匹のペースで次々と入ってきます。離乳していない幼猫は一日に何度も授乳しなくてはならず、一時も目が離せません。

▲ 預かりボランティア中の子猫
その時、大きな助っ人となるのが「預かりボランティアさん」です。
センターでは、猫の月齢、大きさ、状態、頭数などの情報を一斉メールでボランティアさんに送り「預かり」を依頼します。メールを受け取ったボランティアさんは自分に「できることを、できる時に、できる範囲」で、預かりを引き受け、センターに猫を受け取りに行きます。その後、猫の世話や新しい飼い主探しは、預かったボランティアさんがすべてを担い、譲渡へと繋ぎます。
こうした連携レスキューが功を奏し、当センターでは、迅速に命のバトンタッチが行われるため、当センター内で飼育が最も困難とされる幼猫の命も救えるようになったのです。
▶︎神奈川県動物愛護センター登録ボランティア情報
「神奈川県動物愛護センター」のボランティアさんに聞きました。
2011年から9年間にわたり、当センターで猫の「保護ボランティア」を担っている佐藤美樹さん。
以前は犬を飼っていた佐藤さんですが、自宅での預かりスペースなども考え、現在では「幼猫の預かりボランティア」を中心に行っています。
この9年間で佐藤さんが当センターから譲り受け、新しい飼い主さんを探して、譲渡した猫の数は約400頭。
「今年は特に多いです。まだ9月ですが、すでに45頭を引き出して、譲渡しました。普段は、子猫ではなく、成猫を引き出して、ゆっくりとその子にあった飼い主さんを探すのですが、春から秋は出産シーズンなので、必然的に子猫の保護が集中するんです」
そう話す傍らでは、推定2歳の母猫と生後1.5か月の子猫が二匹、楽しそうに遊んでいます。
「この親子は、一か月ほど前に、三匹一緒にレジ袋に入れられ、公園に捨てられていたんです」

▲ 猫の「保護ボランティア」を担っている佐藤美樹さん
その後、所有者不明でセンターに収容された親子猫。佐藤さんに保護され、九死に一生を得ました。
すでに母子には新しい飼い主さんが見つかり、近く譲渡となる予定ですが、保護ボランティアをしていて、譲渡の時のマッチングを見極めるのは簡単ではないといいます。
「実は、以前、マッチングミスをして、保護した子猫にとても辛い思いをさせたことがありました」
それは、佐藤さんが知り合い経由で、譲渡した飼い主さんと子猫のテツくんとの出来事です。
「とてもいい人で大切にしてくださると思ってお渡ししたのですが、“しつけ”と考えたのでしょうか。テツくんが飼い主さんの意のままにならないと、首根っこを捕まえて叩くようになり、テツくんは人を見ると唸ったり咬んだりするようになったんです」
相談を受けた佐藤さんはすぐにテツくんを返してもらうことに。
「お渡しするまでは普通のとてもかわいい子猫だったのに、返ってきた時には、唸る、咬む、逃げるとすっかり人間不信に陥っていました。私の力ではどうにもならず、動物行動学専門の先生に半月間預かってもらうことにしたのです」
その後、ようやく人間への信頼を回復した、テツくん。今では新しい家族と幸せに暮らしています。
「何年やっても、例え400匹を保護し、譲渡へ繋げても、ひとつとして同じ命はありません。どの子にもとびっきりの家族を見つけてあげたい。そのカギとなるのが飼い主さんとのマッチング。命は救って終わりではなく、その子のことをよく理解し大切にしてくれる飼い主さんのもとで、ずっと幸せに暮らしていけるよう、保護猫との約束を果たすことが、本当の意味での “命を救う” です」

▲ ボランティア宅で遊ぶ保護猫の親子
保護ボランティアさんの多くもそうですが、佐藤さんは、譲渡した後の様子もきちんと報告を受け、家族として幸せにしているかどうかを必ず確認していると言います。
保護ボランティアを続けてきたこの9年間を振り返り、佐藤さんはこう締めくくりました。
「長く続けるためには、できることをきちんとやること。そしてできないことはできないとお断りすること。それに尽きます。そうしないと自分が壊れる(笑)。どの子も救いたい、という気持ちはみな同じですが、私個人で保護できる命の数には限界があります。すべての命を救えるわけではありません」
そんな思いを知ってか知らずか、最近、佐藤さんは時々、周囲でこんな言葉を耳にすると言います。
「神奈川県は殺処分ゼロで良かったね!すごいよね!」
この「ゼロ」が誰も何もしなくても達成できていれば「良かったね」で済むでしょう。
しかしこの「ゼロ」は、佐藤さんのような人たちの力で達成できていることを忘れてはなりません。
もし今後、神奈川県動物愛護センターに収容される犬猫の数が急増したら職員さんや、ボランティアさんの手に負えず、「命の椅子取りゲーム」が始まります。そして、その椅子からこぼれおちた命には「死」が待っています。
本当の「ゼロ」とは、捨てられる命が「ゼロ」となること。
動物愛護センターに収容される命が「ゼロ」になること。
ボランティアさんたちの嘘偽りない気持ちです。
「神奈川県動物愛護センター」課長の上條さんに今後の課題を聞きました!
この度、取材に応えてくださったセンター課長で獣医師の上條光喜(かみじょう こうき)さん。
今後の目標や課題について、お聞きしました。
「いのち基金もそうですが、ここにいる犬猫の家族をいかに上手に見つけてあげるかが、課題です。現在も職員手作りのPOPを作ったり、多くの情報を提供することで、譲渡推進を進めていますが、さらなるバージョンアップのため、譲渡推進プロジェクトを企画しています」
これは、センターで飼い主募集をしている犬猫たちを家庭に迎え入れてもらうためのPR事業。ウェブサイトや動画などを用いて、保護犬猫たちのPRを継続的に行い、多くの人たちに家族として迎えてもらえるよう考えたプロジェクトで、今年度中に実施予定です。

▲ センター課長の上條光喜さん
「いのち基金」や新プロジェクトを基盤に、保護される犬猫たちの受け皿万全の当センターですが、現代ならではの問題も―。
「これは今の孤立した人間関係を反映した社会問題なのかもしれませんが、今後不安なのが猫の多頭飼育崩壊です」
多頭飼育崩壊をした猫を保護するとなれば、一度に収容される数は数十匹から時には100匹を超えると予測されます。
また、多頭飼育されている猫は手入れもされていないことも多く、病気や怪我をしている猫も多いと言います。
一度に数十頭単位の猫が収容されれば、現場の混乱は避けられません。
「今の世の中、自分と違う人を容認しなくなり、孤立が深まる。そんな中、心の支えとして猫を飼い始め、結果的に1頭、1頭を大切にできないまでに増やしてしまう―。今後はそんな猫たちが多く出てくるのでは、と心配でなりません」
捨てられるペットの命の問題は、動物の問題ではなく、人間社会の問題です。
人間が問題やトラブルを作れば、当然、人間に飼育されている犬や猫にも降りかかります。
飼い主が家庭で喧嘩をすれば、犬や猫は怯えます。
飼い主が貧困に陥れば、犬や猫も飢えます。
飼い主が病めば、犬や猫も病むことになります。
飼い主が死ねば、犬や猫も行き場を失います。
犬や猫が幸せに暮らすためには、まず私たち人間同士が、より良いコミュニケーションを取り、互いを助け合い、思いやり、良い社会を築き上げあること。
人間が心穏やかで幸せな、毎日を過ごすよう努力することです。
それが「命を預かった責任」ではないでしょうか―?
それが、本当の「ゼロ」への第一歩ではないでしょうか―?
社会的弱者が幸せな社会は、すべての人が幸せな社会です。
つまり―、「動物が幸せな社会は、きっと人も幸せな社会」ということなのです。



取材・記事:今西 乃子(いまにし のりこ)
児童文学作家・特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会理事
主に児童書のノンフィクションを手掛ける傍ら、小・中学校で保護犬を題材とした「命の授業」を展開。
その数230カ所を超える。
主な著書に子どもたちに人気の「捨て犬・未来シリーズ」(岩崎書店)「犬たちをおくる日」(金の星社)など他多数。