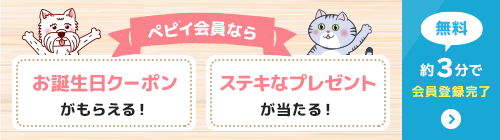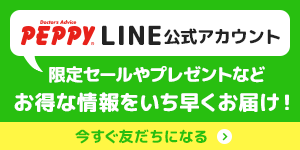VOL.13 横須賀市動物愛護センター 編
キーワードは「行政と地域住民との信頼関係」
住民との「信頼」・「相互理解」から「真の動物愛護」を目指す施設
横須賀市追浜運動公園に隣接する横須賀市動物愛護センター。
平成21年に開設されたこの施設は、小規模でとてもコンパクトなつくり。
人口39万人のこの街は、平成13年4月に中核市となり、犬猫の飼育率は約7世帯に一世帯。現在では、収容される犬や猫も少なくなっています。
管理の仕事が少なくなれば、愛護業務に力を注げる―。
同センターが、現在、最も力を入れているのは「地域猫プロジェクト」への地域住民からの理解と同センターで開催する親子イベントや、学校での「出前授業」などの子どもたちへの動物愛護啓発事業です。

その中でユニークなのが、NPOと協力して実現した動物愛護の「音楽劇」。
歌とお芝居で、子どもたちに動物愛護の心を伝える同センターの活動と、地域住民の心を動かす「地域猫プロジェクトの啓発事業」をご紹介します。

目次
・横須賀市動物愛護センターのここがポイント
センターの歴史を振り返り、官民の役割を明確化して、「真の動物愛護」を目指す
・横須賀市動物愛護センター、子どもたちへの啓発活動
同センターと共に活動を続けるNPO法人「みゅーまる」さんに聞きました!
・横須賀市動物愛護センターの課題は、「地域猫」の啓発活動
「猫が好きな人」VS「嫌いな人」では、問題は解決しない
横須賀市動物愛護センターのここがポイント
センターの歴史を振り返り、官民の役割を明確化して、「真の動物愛護」を目指す
横須賀市動物愛護センターは、他のセンターに比べ、非常に小規模ながら必要な設備がすべて整った施設。玄関を入れば動物愛護イベントを行う多目的ルームがあり、訪れる人に明るい雰囲気を与えてくれます。
反面、昨今では多くの動物愛護センターが殺処分機を置かない中、ここの動物保護管理棟には殺処分機があり、動物愛護業務だけではなく、管理業務体制もしっかり整っていることがうかがえます。
「愛護センターという名前で誤解されている方も多いかと思いますが、ここの業務で一番大切なのは管理業務。まだここが動物管理所だった平成11年頃には、犬を約200頭、猫に関しては収容され1000頭のうち997頭を殺処分していました。でも時代は変わり、動物愛護センターでの犬猫殺処分は全国的に見て、この10年間で約10分の1まで減っていきました。
この変化に大きく功を奏したのが、動物保護ボランティアさんの存在。
以前は“殺処分するな!”と保護団体からの苦情が非常に多かった。管理を第一に考える行政と、愛護を第一に考える保護団体とは、担っている役割が違うため、歩み寄ることが難しい。しかし現実的には彼らのおかげで殺処分数が激減したと言っても過言ではない。
行政ではできないことをボランティアがしてくれたからこそ今があるんです。彼らには本当に感謝の言葉しかありません」

▲所長の高義さんと保護されている柴犬
そう話してくれたのは、同センター所長で獣医師の高義浩和さん。
高義さんは、動物愛護センターの前身「動物管理所」時代から計17年間、センター業務に携わってきました。
「センターに収容された犬猫を引き取り、自宅等で預かって飼い主探しをしてくれる保護ボランティアさんと行政との間で最も大切なのは信頼関係です。
彼らの活動を行政の業務として行うことはできない。できない部分を彼らに補ってもらい、犬猫にセカンドチャンスを与えてもらうわけですから、多少の意見の食い違いはあっても、行政としてできるだけのことはサポートしたいと思っています。
おかげさまで、当センターと保護ボランティアさんとの関係は至って良好。これもお互いの理解と信頼があってのことです」
現在では同センターも、ペットの処分で殺処分機が稼働することもなく、収容動物も年間約130頭(令和二年度実績)と少数。
収容動物が減った分、同センターも多くの時間を、個々の収容動物のケアや動物愛護業務に使えるようになりました
そこで、力を注いでいるのが親子向けの「動物愛護啓発事業」です。
同センターではNPO法人「みゅーまる」(※1)と協力して、「動物愛護センター開放デー」のイベント時や、地元の小学校への「出前授業」で、音楽劇を取り入れたユニークな手法で子どもたちに「命の大切さを伝える活動」を積極的に行っています。
また「動物愛護センター開放デー」ではイベントの後、動物保護管理棟を見学する「バックヤード・ツアー」も開催。収容保護された犬猫の様子を見てもらいます。
しかし、現在の動物保護管理棟で収容されているのは、とてもきれいに手入れされ、新しい家族を待っている犬猫ばかり。
殺処分を待っている犬猫を目の当たりにすることはほぼありません。
「わたしがこの施設を案内する時、とても明確にしていることがあります。
それは“ここはペットショップではない”ということ。時と場合によってはこの子たちを殺さなくてはならないというのもこの施設の仕事だということです。ここを訪れた人には、殺処分反対やかわいそうという気持ちを持つ前に、どうしてこの子たちがこの施設に入っているのかを考えてほしい。そんな気持ちで啓発に力を入れています。」
その他にも「地域猫」を広く取り入れるため、自治会や町内会へも出向き「飼い主のいない猫と人とのより良い共存」を、行政の役割として広く呼び掛けています。
▲同センターが発行する啓蒙チラシ
(※1) NPO特定非営利活動法人「みゅーまる」
元劇団四季のメンバーを中心に、プロの歌手、俳優による音楽劇、ミュージカル、コンサート、朗読などの上演、幼稚園、小学校、高齢者施設訪問、動物愛護イべントへの参加など、多岐にわたる活動を展開。
https://myu-maru.org/(外部サイトにリンクします)
横須賀市動物愛護センター、子どもたちへの啓発活動
同センターと共に活動を続けるNPO法人「みゅーまる」さんに聞きました!
ミュージックとアニマルを掛け合わせて名付けられたNPO「みゅーまる」は、動物をテーマに音楽と組み合わせ、横須賀市を拠点に動物愛護の啓発活動をしているNPO団体です。
元劇団四季でミュージカルの舞台に立っていた「みゅーまる」理事長の岡本和子さんが横須賀動物愛護センターのことを知ったのは、平成21年。
センター開所のお知らせを地元新聞で見たことがきっかけでした。
「その頃、劇団四季を辞めて間もない頃だったので、犬猫のために何かしたいなと思い、センターでボランティアをしたいと思ったんです。すぐにセンターを訪ね、当時の所長さんと世間話をしているうちに、所長さん自身もバイオリンが好きで、音楽にとても興味を持っていることを知りました」

▲NPO法人みゅーまる理事長の岡本和子さん
音楽という共通の話題で意気投合した二人。岡本さんはその後、音楽で「命の大切さ」を子どもたちに伝えられないかと動物愛護をテーマにした音楽劇を同センターの啓発ツールとして提案しました。
こうして、劇団四季のスタッフと岡本さんが協力して台本を書き、何度もセンターとやりとりして出来上がったのが「ぼくの声がきこえる?」(※2)です。
これは、保健所で殺処分されてしまった犬の“ジョン”が、天国へ渡る“虹の橋”から、大好きだった飼い主の“お姉ちゃん”にやさしく話しかけるお話。
終生飼養や毎日のお世話、命の大切さを、犬の“ジョン”の目線でやさしく伝える親子向けの音楽劇です。
「動物にも心があり、わたしたち人間と同じ命を持っています。子どもたちに誰かを大切にしたり、愛したりすることのすばらしさを理屈ではなく、心で感じて欲しい」
同センターの協力で、ようやくプログラムが完成し、平成23年から同センターで啓発イベントの舞台に立つ岡本さん。
年三回の「動物愛護センター開放デー」ではセンター内のイベントホールで「キッズコンサート」「歌とお話」「音楽劇」などを行う他、センターの職員さんと共に地元の小学校へも出かけます。
プログラムもとてもユニーク。ミュージカル出身の岡本さん達はまず「キッズコンサート」で動物の歌や子どもたちが大好きな歌を、手遊びを取り入れながら一緒に歌います。
子どもたちは夢中で大はしゃぎ!
みんなの気持ちが盛り上がったところで、センターの職員さんのお話にバトンタッチして、センターでのお仕事のことを学びます。
勉強コーナーが終わると最後の音楽劇「ぼくの声がきこえる?」で、命についてじっくりと考えてもらい、プログラムは終了です。
出前授業のあとには、子どもたちから多くの感想文がセンターや岡本さんのもとに届きます。
「一番うれしいのは、イベントや出前授業で見た音楽劇をきっかけに、子どもたちが家族と話し合って、動物愛護センターにいる犬猫を家族に迎えてくれること。啓発活動は草の根活動ですが、まず伝えること、知ってもらうことで、その先の未来は必ず変わっていきます」と岡本さん。
自身も同センターから引き取った犬猫たちと暮らしながら、センターと協力して啓発活動を続けています。
▲朗読と歌を合わせたキッズコンサートの様子
(※2) NPO法人みゅーまるによる音楽劇「ぼくの声きこえる?」
https://www.youtube.com/watch?v=NEA7CLO8vh8(外部サイトにリンクします)
*注)現在、新型コロナ感染症予防のため、イベント及び出前授業に関してのスケジュールは未定です。
同センターまでお問い合わせください。
横須賀市動物愛護センターの課題は、「地域猫」の啓発活動
「猫が好きな人」VS「嫌いな人」では、問題は解決しない
同センターも他のセンター同様、野良猫対策は現在の大きな課題となっています。
飼い猫で、室内飼育をしていれば、なんら問題ない行動、例えば「排泄」「鳴き声」なども、飼い主がおらず管理されないまま住宅街で生活を始めれば、住民からの苦情が挙がり社会問題へと発展します。

また「地域猫」活動に率先して取り組むのは多くが愛猫家で、つい「猫目線」の対策になりがちです。
しかし、それでは問題はエスカレートするだけで、解決には至らないと高義さん。
同センターでは、職員が地域猫活動を取り入れたいと考える町内会や自治会に出向き、主に猫の嫌いな人や無関心な人たちに向けた啓発活動を積極的に行っています。
■同センター高義さん流「猫が嫌い・猫に無関心」な人たちへの啓発活動とは―?
所長の高義さんのお話をもとに、解決策をイメージで再現してみました!







高義さんが考える「地域猫プロジェクト」の大切なポイントとは―?
- ①猫嫌いの人に「猫好きになってほしい」という望みを持たず、
猫が嫌いな人でも「まあ、猫が歩いていてもいいか」と思ってもらえる結果を目指すこと。 - ②「猫嫌いが2人」「どちらでもないが6人」「猫好きが2人」。
計10人の住民がいたとすれば、「どちらでもない6人」が「猫嫌い」にならないよう
相互理解と、譲り合いで、地域対策を急ぐこと。
「地域猫プロジェクトがきちんと事業として地域で成功すれば、猫の数は減ります。数が減れば、やっかいものからマスコットとしてかわいがられるようになるでしょう。
地域猫としてお世話をしてくれた猫好きさんが、地域猫として最後に残った一匹を家族として迎え入れてくれた、というケースもあります。
センターでの管理業務もそうですが、数が増えると愛護にまで手が回らなくなる。やっかいものになってしまったのは、数が増えすぎたからです。これは地域猫だけではなく、多頭飼育で問題となっている飼い主さんも同じでしょう」
犬や猫は野生動物ではありません。わが国で犬猫はペットという役割を位置づけられているのです。ならば預かった命には責任を持って一生涯の面倒を見るのが、飼い主としての責任。逆に責任が持てる以上の命(多頭)を飼わないことも、飼い主としての責任ではないでしょうか。

横須賀市動物愛護センター所長さんの今、伝えたいこと
自らも同センターに収容された子猫を引き取り、現在8歳になるオス猫ニャッキ―と一緒に暮らす高義浩和さん。動物愛護センターという施設が「殺処分の施設」と言われた時から「命を繋ぐ施設」と言われる現在に至った今の思いをこう語ります。
「現在は動物愛護法により、飼い主の身勝手な都合で犬猫の飼育を放棄する場合、センターは引き取りを拒否することができます。殺処分ゼロがブームのように騒がれる今、行政もそのことにとても敏感になっている。引き取りを拒否すれば当然、犬猫の収容数も減り殺処分も減りますが、それが逆に遺棄に繋がる。
つまり、“収容数が少ない”とか“殺処分ゼロ”とか、世間体を気にして、数字にこだわるのはとても危険だと思っています。決して、犬猫のためにはなりません。

▲所長の高義浩和さん
人間が飼った生き物ですから、同じ人間として責任を持って、何が犬猫の福祉につながるのか、私たちは考えなくてはならない。
引き取り拒否ではなく、引き取る方が犬や猫のためになるのなら、断らず引き取る覚悟も必要なんです。
ぼくはこれまで、センターの管理業務としてたくさんの犬や猫の処分に関わってきた。
殺すのは一瞬で終わる。
でも命とは、助かって“ああ、よかった”ではなく、助かったその先がスタートなんです。
そのスタートはすべての命にとって幸せで輝かしいものでなくてはならない。その命の行方を左右しているのは飼い主なんだということを忘れないで命と向き合ってほしいと切に願っています」


取材・記事:今西 乃子(いまにし のりこ)
児童文学作家/特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会理事/公益財団法人 日本動物愛護協会常任理事
主に児童書のノンフィクションを手掛ける傍ら、小・中学校で保護犬を題材とした「命の授業」を展開。
その数230カ所を超える。
主な著書に子どもたちに人気の「捨て犬・未来シリーズ」(岩崎書店)「犬たちをおくる日」(金の星社)など他多数。