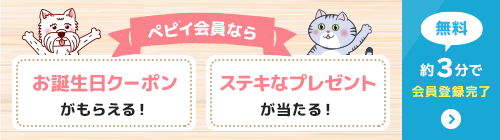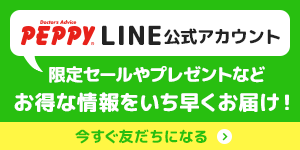【連載コラム】シニア犬・シニア猫と暮らす Vol.14


-

ぬのかわ犬猫病院

シニア犬との暮らしを、もっと楽しく、もっと豊かに!
その魔法は、飼い主さんの「心」にあった。
飼い主さんの「心」ひとつで、シニア犬の「心」も、
こんなに元気にイキイキ輝く!
令和5年、全国犬猫飼育実態調査によると、犬の平均寿命は約14.62歳で、過去最長を記録。
愛犬の長生きは、飼い主さんにとって大きな喜びですが、そこで直面する老犬のお世話や介護は、まだまだ分からないことも多く、飼い主さんにとっては試行錯誤の連続です。
「うちの子はまだまだ若いから、介護なんて先のこと!」と思っている飼い主さんにとってもいずれは訪れる愛犬の老後-。
早いうちから様々な知識を身に着け、介護の概念だけに縛られず、考え方を転換することで、愛犬の老後は私たちにとっても、愛犬にとっても、ハッピーでほのぼのとした日々に変身します。
今回は、シニア犬のエキスパート、ぬのかわ犬猫病院の総看護師長で、愛玩動物看護師の三橋有紗さんに、シニア期の愛犬と楽しく暮らす様々なコツや、シニア期を迎えるための日ごろの準備やケアなどについて詳しく聞いてみました!

シニア犬のエキスパートを目指して!
子どもの頃から犬が大好きだったという動物看護師の三橋有紗さん(35)。
三橋さんは、自宅がマンションでペット飼育不可だったため、学校の帰りなどで出会った犬や近所の犬を片端から撫でて写真を撮る幼少時代を送っていたといいます。その頃から「将来は必ず犬に関係する仕事に就く」と自分自身に誓い、その後は迷うことなく動物看護師の道を選びました。
-
そしてそれは念願叶い、「ぬのかわ犬猫病院」で動物看護師として働き始めて一年目のこと。ようやく仕事に自信を持ち始めた三橋さんは、病院のホテルを利用するために預かったマルチーズの世話を任せられることになったのです。
「年齢は18歳くらいで、寝たきりの子でした。いつ死んでもおかしくないくらいのハイシニア。当然お世話には介護が必要ですが、具体的に何をどうすればいいのかがわからない。先輩たちに聞いても、答えは様々で、みなそれぞれが、なんとなくこんなことをやっているというレベルで、現場でも老犬介護の方法がまだきちんと確立されていなかったんです」 -

老犬介護とは何か?正解はあるのか?
寝たきりの犬に水一つ飲ませるにも四苦八苦して、正しい飲ませ方がわからず悩んだ三橋さんは、このマルチーズとの出会いをきっかけに「シニア犬について徹底的に勉強しよう」と一念発起!自分なりに猛勉強を開始しました。
「その頃(15年ほど前)は、犬の介護やシニア犬との暮らしは、未知の世界・・・。犬の平均寿命が年々伸びていくにつれて、今後は、多くの飼い主さんが直面する課題だと感じました。とにかく勉強しかないと、病院に訪れたシニア犬の飼い主さんに、診察後に片っ端から聞き取りを開始し、情報をどんどん収集して、シニア犬のオリジナルカルテを自分で作ることにしたんです。例えば、ある日、シニアの柴犬が、一時的な検査でやってきたのですが、待合室でもグルグルと同じ場所を回る行動がありました。その様子を見て、病院の中だけではなく、自宅での普段の様子もできるだけ詳しく飼い主さんに聞いてみることにしたんです」
すると、飼い主さんは、かかりつけで、顔なじみの三橋さんに「待っていました」と言わんばかりに、自分たちの介護の苦労を話し始めたと言います。
-
「夜は鳴きながら、グルグル自分たちの足の周りをまわるので、家族みんなで交代しながら面倒を見ているのですが、朝までひたすら同じ行動が続きます・・・家族みんな寝不足で、本当に辛いです」飼い主さんは苦しみを吐き出すかのように三橋さんに訴えました。
中には、涙ながら話をする飼い主さんも・・・。
三橋さんは、次々とシニア犬の飼い主さんの話を聞いていくうちに、介護がいかに飼い主さんにとって大変なことで、飼い主さんがどれほど頑張っているのかがわかったと言います。 -

一年間に渡りシニア犬の飼い主さんから情報収集した三橋さんは、独自のカルテのデータをどんどん増やしていきながら、病院に入院しているシニア犬やホテル利用のシニア犬の世話を自ら率先して担当したいと、病院に申し出るほどになりました。
「シニア犬の世話は病院でも大変な役割。それでも経験をたくさん積んで、シニア犬のことをできるだけ勉強したかった。診察後の飼い主さんへの聞き取りで時間をかなり費やしたこともありますが、飼い主さんのメリットになることであれば、病院側もやりたいことを全力で応援してくれました。病院や周囲の理解があったことも、ありがたかったですね」
こうして、三橋さんは、シニア犬のパイオニアとしてその道を究め、今ではシニア犬のエキスパートとして、多くの関係者に知られるようになったのです。
若犬飼い主さんへのアプローチで、共にハッピーなシニア期を目指す!
現在、三橋さんは病院内でアシスタント1名と共に、少人数制のシニア教室を設けています。
(不定期開催 ぬのかわ犬猫病院のHPにてご確認ください)
教室に参加する多くの飼い主さんが、当病院かかりつけ。シニア教室といっても、普段の通院でみな馴染み深く、若い犬たちも多く参加しています。
「愛犬が若い年齢で参加する飼い主さんの多くは、シニアになったら自分の犬がどんな状態になるのか今後のために知っておきたい、という理由です。教室では実際に参加しているシニア犬の状態を見ることができて、シニア犬の飼い主さんから介護のことなどいろんな話を直に聞くことができます。飼い主さん同士の情報交換の場所にもなり、この教室で、飼い主さん同士が連絡先を交換することで、飼い主さん同士が直接相談し合ったり、情報交換できるきっかけづくりにもなっています」
-
シニア教室では、愛犬のシニア度をチェックした上でのリハビリやマッサージ、愛犬が不自由なく暮らすための環境づくりのアドバイス、など、フィジカル面でのサポートも行いますが、三橋さんが最も力を入れているのが、飼い主さんのメンタルケアです。
「飼い主さんの中には、愛犬の老いを受け入れられない人も多い。そんな飼い主さんが他の飼い主さんと交流することで、愛犬の老いを徐々に受け入れるようになれる。また、教室を通して、私たちとの信頼関係が深まれば、飼い主さんの方から、私たちにいろんな話をしてくれます。あくまでこちらから、こうすればいい、ああすれば大丈夫、などという一方的なアドバイスや介入はせず、向こうから心を開いて話してくれる機会を大切にし、相談事があれば全力でサポートします」 -

そんな三橋さんの手法は、飼い主さんのメンタルケアに大きな効果をあげています。
「ハイシニア犬になると、認知症を発症したり、排泄の失敗があったり、散歩や歩行の補助が必要になったり、さらには寝たきりになったりと、若い頃の愛犬とは比べ物にならないほど世話が増え、世話の時間も膨大になります。
真面目でいい飼い主さんほど、頑張ろうと無理をする。そして完璧な世話ができていないと思うと落ち込んで、犬に対して申し訳ないと思ってしまう。そしてさらに頑張ろうとするのですが、時間も足りない、手も足りないとなるわけです。するとさらに落ち込んで、精神的に追い込まれ、中には鬱病を発症する人もいる。負のスパイラルに陥ります」
-
そんな状況から一転、シニア犬のお世話をハッピーにするためには、飼い主さんの考え方の転換が不可欠。ここからが「三橋流シニア介護」のすすめです。
「介護には、棲み分けが必要。フィジカル面は、私たちプロを大いに頼ってほしい。そして飼い主さんは、愛犬に愛情を精一杯注ぐことに全力を尽くしてほしい。飼い主さんが落ち込むと愛犬もそれを見て落ち込みます。愛犬がメンタル面でも弱っていくと、フィジカル面でも弱っていく。愛犬を元気にしたいのなら、飼い主さんが毎日笑顔で元気でいることです。
例えば介護で睡眠不足になりへとへとに疲れているのなら、私たちに愛犬を2,3日預けて、飼い主さんにはしっかりと休養をとってもらい、元気に笑顔を取り戻してもらうこと。それだけで、シニア犬と飼い主さんのQOL(生活の質)は、抜群に上がります。 -

-
私たちプロは、お世話を担うことはできますが、大好きな飼い主さんの愛情という点だけは、代わりに請け負うことができません。ですから飼い主さんは愛情一本!それ以外はプロに頼ってくれていいということなんです。
もちろん、お世話面でも介護が必要なシニア犬を別の誰かに託すことは、飼い主さんにとって様々な不安もあるはず。だからこそ、私たちプロと飼い主さんとの日頃の信頼関係が最も重要になってきます。“この人になら大切な愛犬を任せられる”と思える信頼関係が、普段からできていれば、負のスパイラルに陥ることなく、シニア犬との生活を元気にハッピーに過ごすことができるのです」 -

そのためには、愛犬が若い時から、信頼できるプロとの密な関係づくりが必須です。
信頼関係は短期間で築き上げることはできません。シニアになって、誰かを頼りにしたくて慌ててその時、急にお願いしても、互いのことがわからなければ齟齬も生まれやすく、安心して任せることはできません。そうなると、笑顔と元気を取り戻すどころか、さらに不安は大きくなるばかり。その不安を一番感じてしまうのは愛犬なのです。
-
また、犬への声掛けひとつにも、介護面で大きな違いが出ると、三橋さんは言います。
「犬は、飼い主さんしか見ていません。それだけに飼い主さんの表情や言葉には非常に敏感。だから、飼い主さんが “ごめんね” “大丈夫?” “心配だよ”というネガティブな言葉を連発していると、犬にそれが伝わってしまいます。ネガティブな言葉は使わない。愛犬が元気でいるための基本です」
そうアドバイスする三橋さんも「楽しい声掛け」が最初からできたわけではありません。
それは、11年ほど前、病院の供血犬でシェパードの「番長」の世話を担当していた時のことです。ある日、番長の足に異変があり、レントゲンを撮影してみると、骨肉腫であることが判明。治療が絶望で余命僅かと知った三橋さんは番長の前で三日三晩泣き続けました。
番長は、全く食事をとらなくなり、三橋さんが、その姿を見て「そんなに痛いのか」とますます落ち込んだと言います。 -

ある日「番長が食べないのは自分の落ち込んでる姿のせいだ」と思った三橋さんは顔を洗い、その日から笑いながらドライフードをもって「番長!かっこいいな!すごいな!」と言い続けました。すると、シュンと垂れ下がっていた番長のシッポが上がり、クルンクルンと回ったかと思うと、フードをガツガツと食べはじめたのです。それを見た三橋さんがうれしさのあまり、さらに笑顔になると、番長は病気で弱っているにも関わらず「おかわり」までしてどんどん食べるではありませんか。番長にとって、三橋さんの笑顔は何よりの特効薬だったのです。
その後、余命宣言より長く生きた番長とのこの体験は、三橋さんに、愛犬介護の決定的確信をもたらすことになりました。
“ 飼い主の愛情と、笑顔こそ、愛犬にとっての特効薬!
飼い主の笑顔なくして、いい介護はない― ”
シニア犬に残された時間は限られています。
最後がいつくるか、わからないからこそ、飼い主さんが常に笑顔でポジティブな声掛けをし、最期を迎えるまで、楽しい思い出を積み重ねていくことが大切なのです。
介護の目標は臨機応変に
これまでできたことができなくなるシニア犬のライフステージは日々変化し、その変化に合わせて、飼い主さんは様々な介助や介護を担わなくてはなりません。
-
例えば散歩。足腰が弱って来た愛犬のために補助具をつけたり、腰を支えたりしながらの散歩は、ハイシニア犬を飼っていた人ならだれでも経験があることです。
そして、散歩の補助のため、飼い主さん自身が足腰を痛めてしまうことも、ハイシニア犬飼育経験者にとっては「あるある」です。
愛犬が外で歩きたい、という気持ちを優先するあまり、飼い主さんは無理をしてでも一所懸命頑張ってしまうのです。 -

しかし、そこにも介護をしていく上での発想の転換が必要だと三橋さんはアドバイスしています。
「例えば大型犬の介護で、補助が必要な場合、飼い主さんは少しでも歩かせてあげようと頑張りますが、それで、飼い主さん自身が腰痛を悪化させたり、ヘルニアになって動けなくなってしまって、辛い思いをしていては逆効果。飼い主さんの笑顔が大好きな愛犬のためには全くならないということです。そこで介護の目標を “たくさん歩かせる” から “外に出てひなたぼっこ” にする、と目標を変えることで、飼い主さんも負担なく、笑顔で、介護をすることができます。カートに乗せて散歩する、とかもいいですね。何が何でも散歩させなくてはならない、と考える必要はありません。介護の目標を何にするのかを、飼い主さん家族で、ステージごとに話し合って、担っていくのがベスト。介護にこれが絶対正解という答はありません。自分の犬の介護の目標を、家族みんなで話し合い、臨機応変に担っていくことが大切なのです」
ペットロスは、シニア期との向き合い方で、大きく変わる
飼い主さんの誰もが最後に経験する愛犬との別れ・・・。
愛犬を天国に見送った後に訪れる喪失感、いわゆる「ペットロス」は多くの飼い主さんが経験することです。
このペットロスもシニア期の愛犬との向き合い方が大きく左右されると三橋さんは言います。
-
「介護でくたくたになっていると、飼い主さんは、ふと心のどこかで “もう愛犬が亡くなってしまってもいい・・・”と考えてしまい、その直後に、そんなひどいこと考える自分は最低だ、と自己嫌悪に陥ることが少なくありません。人間追い詰められると、そういう心理状況になってしまう。
そんな心境の中で愛犬が天国に行ってしまうと、飼い主さんは自分を責めて嫌悪し、愛犬の死から立ち直れなくなる。愛犬に対して後悔が多い人ほど、ペットロスに陥り回復が難しくなってしまう傾向があります」 -

-
大切なのは、愛犬の老いの変化を早い段階から受け入れ、必要な時はプロの手に介護を委ね、心にゆとりをもって、愛犬にこれまでと同じ愛情を注ぐこと。
「まだまだ元気!まだまだ大丈夫!」と、現実から目を背けていると、いよいよとなった時、愛犬の変化に、心がついていかなくなるため、年齢ごとのライフステージにあった受け入れを、飼い主さん自身のフィジカル面でもメンタル面でも準備しておくことが大切なのです。 -

「愛犬を失って寂しくない人は誰もいません。でも、シニア期を愛犬と悔いなく、笑顔で楽しく過ごし、きちんと見送ることができれば、愛犬を失った“辛さ”はやがて自然と消える。一番やっかいなのは、“後悔”です。これがペットロスを延々と長引かせるのです」
どんなに後悔しても、亡くなった愛犬は二度と生きて帰っては来ません。
だからこそ、生きている間に、ひとつでも多くの楽しい思い出を作っておくことが大切です。その楽しかった愛犬との思い出と共に、私たちはその先も笑顔で生きていくことができるからです。愛犬と共に過ごした飼い主さんの十数年間の思い出は、愛犬抜きにして語ることができないもの。ならば、笑顔になれるような思い出をたくさん作っておくことで、私たちは天国にいる愛犬のことを、これから先もずっと、笑顔で思い出すことができるのではないでしょうか―?



(取材:2024年10月)
神奈川県横浜市戸塚区下倉田町273

取材・記事:今西 乃子(いまにし のりこ)
児童文学作家/特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会理事/公益財団法人 日本動物愛護協会常任理事
主に児童書のノンフィクションを手掛ける傍ら、小・中学校で保護犬を題材とした「命の授業」を展開。
その数230カ所を超える。
主な著書に子どもたちに人気の「捨て犬・未来シリーズ」(岩崎書店)「犬たちをおくる日」(金の星社)など他多数。